江戸時代の暦法
太陰太陽暦
近世以前の暦は、陰暦を用いていました。
陰暦では、1ヶ月の長さを月の満ち欠けによる朔望月(太陰月。29.53059日)を基礎とした12ヶ月を一年としていました(大の月は30日、小の月は29日で、暦の1年の日数は29.5×12=354日となりました)。太陰暦の1年は1太陽年(365.2422日)より日にちが少なくなってしまうため(※1)、二・三年に一度、閏月を入れなければなりませんでした(1年で11日、2年で22日、3年で33日違いが生じてしまうわけで、第3暦年(註:太陽暦の3年ではありません)を13ヶ月とすれば季節の狂いが減らせました)。閏月を含む年を閏年を呼びます。
旧暦の日付は月の形状と対応していました。陰暦第三夜に出ることから名づけられた「三日月」、躊躇うように出ることから「いざよい」と名づけられた第十六夜の既望の月を「十六夜(の月)」と書くことなどがその例です。
暦は何度か作り替えられました。八六二(貞観四)年からずっと宣明暦が用いられていましたが、貞享元年(1684)に宣明暦が廃止され、翌年から貞享暦が施行されました。その後寛政10(1798)年に施行された寛政暦、天保15(1844)年に施行された天保暦があります。天保暦は、太陽暦が採用されるまで用いられました(※2)。
※1…365.2422日-354日で、11.2422日短くなる計算です。
春秋時代の頃に19太陽年(365.2422日×19年=6939.6018日)≒235朔望月(29.53059日×235月=6939.6886日。235朔望月=12ヶ月×19年+7ヶ月)が分かり、19年に7回閏月をおくようになりました(十九年七閏の法/メトン法)。
※2…太陽暦を用いるようになったのは明治5年12月から。
※ 1ヶ月・1月という呼び方自体、暦の基準が月の満欠にあったことを表しているといえるでしょう。『日本語源大辞典』(校倉書房)には、月という語について「『時』という語と同源であろう」とあります。
[月の運行]
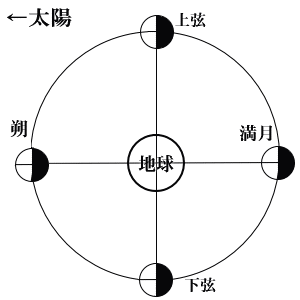
朔(新月)は陰暦で月の第1日目。「月が立つ」ため「つきたち」→「ついたち」と呼びます。
3日目くらいに見えるのが三日月。
上弦の月は陰暦で毎月7日・8日頃。満月は15日目頃。
満月を過ぎると月の出は次第に遅くなり、形も欠けてゆきます。
16日を十六夜、17日を立待、18日を居待、19日をに寝待、20日を更待と呼びます。
月の入りも次第に遅くなり、残月(有明月)が見られます。
下弦の月は陰暦で22日・23日頃。29日・30日目の月は見えません。
「月が籠もる]ことから「つきごもり」→「つごもり」。月の末日を「みそか」とも呼びますが、これは30日(三十=みそ、日=か)からきています。
干支(十干十二支)
五行(木・火・土・金・水)を陽(兄)と陰(弟)に分けたものが「十干」です(木の兄を甲(きのえ)、木の弟を乙(きのと)と呼びます)。
十干と十二支(子・丑・寅・卯……)を組み合わせ、甲子・乙丑……というように表していくと、六十組が出来ます。これを干支と呼びます。
六十歳のことを「還暦」と呼ぶのは、六十年で干支の一サイクルが終わり、再び自分が生まれた干支に戻ることからきています。
干支(十干十二支)表
| 1甲子 | 11甲戌 | 21甲申 | 31甲午 | 41甲辰 | 51甲寅 |
| 2乙丑 | 12乙亥 | 22乙酉 | 32乙未 | 42乙巳 | 52乙卯 |
| 3丙寅 | 13丙子 | 23丙戌 | 33丙申 | 43丙午 | 53丙辰 |
| 4丁卯 | 14丁丑 | 24丁亥 | 34丁酉 | 44丁未 | 54丁巳 |
| 5戊辰 | 15戊寅 | 25戊子 | 35戊戌 | 45戊申 | 55戊午 |
| 6己巳 | 16己卯 | 26己丑 | 36己亥 | 46己酉 | 56己未 |
| 7庚午 | 17庚辰 | 27庚寅 | 37庚子 | 47庚戌 | 57庚申 |
| 8辛未 | 18辛巳 | 28辛卯 | 38辛丑 | 48辛亥 | 58辛酉 |
| 9壬申 | 19壬午 | 29壬辰 | 39壬寅 | 49壬子 | 59壬戌 |
| 10癸酉 | 20癸未 | 30癸巳 | 40癸卯 | 50癸丑 | 60癸亥 |
日本史に登場する壬申の乱、甲午農民戦争、戊辰戦争などは、この干支からその名称がきています。
甲子の年や辛酉の年は災いの年とされ、改元されるのが慣例でした。→江戸時代の元号についてはこちら(別窓)。
月の異名・十二節気(※陰暦による)
太陰太陽暦では暦日と季節の間にずれが生じてしまい、特に農事に関してそのずれは大きな問題となりました。
そのため、「1太陽年を365.25日とし、それを24等分した時点毎(15.21875日)」、または「黄道を15°おきに24等分し、太陽が各分点を通過する時点毎」に特別な名称を与えました。これが二十四節気です(前者の決め方を「平気法」、後者の決め方を「定気法」と呼びます)。
二十四節気には12の中気と12の節気があり、これらを交互に配列し、例えば「正月中」の日を含む月を「正月」、「二月中」の日を含む月を「二月」としていました。中気を含まない月を「閏月」と呼びます。
旧暦は定気法を採用していましたが、定気法では夏と冬とで中気と中気の間の日数に差が出てしまうため、かなり複雑なものとなっていました。
| 季節 | 月 | 月の異名 | 二十四節気 |
| 春 | 1 | 睦月・初春・祝月・孟春・ 正月・元月・初春月・年初月・初空月 |
立春(正月節) |
| 雨水(正月中) | |||
| 2 | 如月・仲春・仲陽・令月・ 初花月・梅見月・雪解月 |
啓蟄(2月節) | |
| 春分(2月中) | |||
| 3 | 弥生・季春・桜月・ 晩春・花見月・花咲月 |
清明(3月節) | |
| 穀雨(3月中) | |||
| 夏 | 4 | 卯月・孟夏・首夏・初夏・ 麦秋・卯花月・花残月 |
立夏(4月節) |
| 小満(4月中) | |||
| 5 | 皐月・仲夏・仲暑・五月雨月 雨月・橘月・早苗月 |
芒種(5月節) | |
| 夏至(5月中) | |||
| 6 | 水無月・季夏・葵月・水月・ 常夏月・晩夏・常夏月・風待月 |
小暑(6月節) | |
| 大暑(6月中) | |||
| 秋 | 7 | 文月・孟秋・新秋・涼月 棚機月・女郎花月 |
立秋(7月節) |
| 処暑(7月中) | |||
| 8 | 葉月・仲秋・清秋・竹春・ 月見月・秋風月・萩月 |
白露(8月節) | |
| 秋分(8月中) | |||
| 9 | 長月・季秋・菊月・晩秋・暮秋・ 紅葉月・紅染月 |
寒露(9月節) | |
| 霜降(9月中) | |||
| 冬 | 10 | 神無月・孟冬・陽冬・初冬・ 時雨月・初霜月 |
立冬(10月節) |
| 小雪(10月中) | |||
| 11 | 霜月・仲冬・陽復・暢月・ 霜降月・神楽月・雪見月 |
大雪(11月節) | |
| 冬至(11月中) | |||
| 12 | 師走・季冬・極月・臘月・ 晩冬・春待月・親子月 |
小寒(12月節) | |
| 大寒(12月中) |
「中」が月の前半にくる場合に、同じ月の「節」が前月に含まれ、次の月の「節」がその「中」と同じ月に含まれてしまうといった事態が生じました。
例えば、「12月中(大寒)」が月の前半にあたり「正月節(立春)」がその月の後半にくる場合などがそうなのですが、このような例を「年内立春」と呼びます。
在原元方の歌に「年の内に 春は来にけり 一年(ひととせ)を 去年(こぞ)とやいはん 今年とやいはむ」(古今一・春上)とあるように、新年と立春がほぼ一致していた(とはいえ、年内立春も珍しいことではなかったようです)旧暦を用いていた時代には、立春になった以上は過ぎ去った年を「去年」と呼ぶべきか、それとも正月になるまでは「今年」と呼ぶべきか、という思いが生じたようです。
時刻
古くは定時法と不定時法の両方がありました。
定時法は一昼夜を十二等分したもので、十二支を用いて表されます。一刻は現在の二時間分にあたり、前の一時間を「初刻」、後の一時間を「正刻」と呼びました。更に、一刻は四つに分けられ(一つ、二つ、三つ、四つと数えます)、例えば「草木も眠る丑三時」とは、丑の四分の三の時を表しました。因みに、日の変わり目は丑寅の間とされ、丑の刻が一日の終わりとされていました。
現在も用いられる「午前」「午後」という言葉は、一昼夜を十二等分し、そこに十二支を振り分けたとき、午の時刻が12時(正午)に当たるため、それより前を午の時刻より前、すなわち「午前」とし、後を「午後」として名付けられた呼び方です。
定時法とは別に、午前・午後を六等分して、夜半及び正午を「九つ」とし「四つ」まで数える方法もありました。
不定時法は、日の出から日没までを昼間とし、昼夜をそれぞれ六等分するもので、江戸時代は一般的にこの時法が用いられていたようです。
この方法だと、季節によって昼夜の長さが変化するため、一刻の長さも変化しました(夏の昼の一刻は二時間より長く、冬の昼の一刻は二時間より短い)。
→ 古時刻の定時法(十二支)と不定時法の図はこちら(別窓)。
→ 古時刻の定時法(六等分)の表はこちら(別窓)。
暦のこぼれ話
旧暦(太陰暦)から新暦(太陽暦)に改暦されたのは明治5年1月9日(新暦では12月9日)。
農村部では農作業の目安となる旧暦が重宝されるなど、庶民は旧暦に親しんでいたので改暦の必要性は感じていなかったようですが、太政官布告が発表され、改暦が断行されました。
しかし政府が改暦を行った理由は、政府が財政難にあったためといいます。役人に12月の給料を払わずに済み、なおかつ閏月分の給料を払わずに済む(明治6年は旧暦だと閏月が生じ、1年が13ヶ月になる予定でした)、結果的に2ヶ月分の給料を節約できるため、この改暦が実施されたのだそうです。
参考
『百科事典マイペディア』(日立システムアンドサービス)、『新世紀ビジュアル大辞典』(学習研究社)、『広辞苑』第五版(岩波書店)、『日本語源大辞典』(校倉書房)、『日本史小百科〈暦〉』(東京堂出版)、大谷光男監修『旧暦で読み解く日本の習わし』(青春出版社)